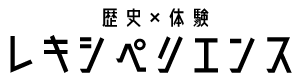その歴史、なんと1000年!「清浄歓喜団」とは
突然ですが「清浄歓喜団」をご存じでしょうか。 一見、どこかの国の団体かと思ってしまいますよね。しかし、実はとっても歴史のあるお菓子の名前なのです。
奈良時代、遣唐使によって日本に伝えられた唐菓子のひとつに団喜(歓喜団)と呼ばれるものがあります。その団喜を日本で唯一再現しているのが、京都の老舗和菓子店・亀屋清永の清浄歓喜団です。名前のインパクトや歴史のわりに、意外と知っている人が少ないこのお菓子。編集部が実際に購入して食べてみました!
「清浄歓喜団」なくして和菓子の歴史は語れない
唐菓子の多くは米や麦などの生地を様々な形にして油で揚げたもので、清浄歓喜団もそのひとつです。本来、日本でお菓子といえば木の実や果物をさしていましたが、唐菓子が伝わり、その意味合いも変わったようです。唐菓子は神仏へのお供え物とされており、当時の一般庶民は口にできませんでした。『枕草子』や『土佐日記』などにも登場しますが、主に貴族が食べるものだったんですね。
日本で唯一”団喜”を再現している「亀屋清永」

亀屋清永では、唐から伝わった八種の唐菓子と十四種の果餅の作り方をもとに再現。十四種の果餅のひとつ「餢飳(ぶと)」とともに販売しています。

編集部が購入した京都祇園にある亀屋清永本店は、八坂神社の近くにあります。店舗は小さいですが、知る人ぞ知る名店という佇まいで、清浄歓喜団を目当てに訪れるお客様も多いようです。
いざ実食!清浄歓喜団の味は?

こちらが実際に購入した清浄歓喜団。略して「お団」とも呼ばれているそうです。特徴的なこのフォルム(なんだか縄文土器みたい…)、八つの結びは八葉の蓮華を表しているのだとか。
食べやすい大きさに割って食べると良いそうですが、生地はそこそこ硬め。筆者はうまく割れずに嚙み砕いてしまいました。
中には7種類のお香を練り込んだ餡が入っていて、食べるとその風味をほのかに感じられます。公式サイトによると、この香には清めの意味があるそうです。現在は小豆餡が使用されていますが、伝来した当初は栗などの木の実をあまづらなどの薬草で味付けしていたといいます。
なにより気になるお味ですが…様々なスイーツを食べなれている現代人にとっては、正直なところ「とても美味しい」とは言えないかもしれません(笑)しかしそのルーツから分かるように、いにしえの味を堪能できる貴重なお菓子です。
清浄歓喜団が購入できる店舗は、祇園本店のほか、京都市では高島屋と伊勢丹のみとなっています。遠方でなかなか直接伺えないという方は、オンラインショップで購入してみてはいかがでしょうか。千年の歴史をもつ清浄歓喜団をぜひ味わってみてください。
亀屋清永
住所:京都市東山区祇園石段下南
営業時間:8時30分~17時
毎週水曜日定休(その他不定休あり)